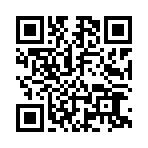2013年09月12日
1892年製のMARTIN 0-28が届く
昨晩の夜8時に、宅急便で、1982年製のMARTIN 0-18が届きました。
今まで、何本もギターを購入して来ましたが
梱包を解く時は、どうかコンデションが良い状態で有って欲しいと
不安と期待が入り交じった状態で、祈りながら、ギターケースを開けます。
ケースは、残念ながら、その当時の棺桶見たいな、コフィンケースでは有りませんが
頑丈なケースが付いています。
ケースの中は、ショックを和らげる為の薄紙が、びっしり詰め込まれています。
大分の骨董屋さんが出品したギターですので、高品質の紙が使われています。
外側から、クラックが無いか入念にチェックします。
どうやら、全体的に塗装がリフィニッシュされているようです。
ブリッジ下に2本のクラックが有りますが、裏側からパッチが充てられ
きちんとリペアされています。
100年以上経っていますので、これ位のクラックは気になりません。
トップのバインデイングに沿って、ヘリンボーンが施されています。
トップ板のアデイロンダックスプルースも、今の材とは木目が全然違います。
ボデイのサイドバックは、その当時ですから、当たり前のようにハカランダです。
クラックは全く有りません。
ヘッドは、スロッテッドです。
ペグは、その当時のオリジナルのようです。
つまみは、どうやら象牙が使われています(ーー;)
100年以上経っているので、使い物にならないと思っていましたが
ちゃんと不具合無く、チューニング出来ます。奇跡です!!
ヘッドの裏には、ニューヨーク時代のMARTINを示す刻印が有ります。
その当時から、MARTINのギターには、ボリュートが付いていたのですね。
ネックは、極太だと思っていたのですが、ナット幅は広いものの
薄い三角ネックで、GIBSONのL-00のように厚みが無く、手の小さな僕でも
とても弾き易いです。
100年に渡る経年変化で、ブリッジ周りのトップ板が膨らんで
弦高が高い上に、サドルが、ぎりぎりまで下げられていますので
ネックリセットが必要です。
この状態は、計算済みですから、心配有りません。
この年代特有のピラミッドブリッジです。
浮いていますが、この状態は、どんなギターでも起こりうる状態ですから
簡単なリペアで済みます。
さて、弾いて見た感想ですが、素晴らしいの一言です!!
ハカランダは、比重が重い材ですが、このギターは信じられない位軽いです。
このギターが作られた時代は、MARTIN社では、ステイール弦が使用されて無く
今で言うナイロン弦使用ですので、全体的に、トップ板や、サイドバックも
とても薄く作られているようです。
内部に手を入れて、ブレーシングの形状を確認しましたが
スキャラップされたXブレーシングでした。
その頃からXブレーシングが使われて居たとは、びっくりです。
コンパウンド弦を使用していても、ボデイばかりで無く、ネックも振動していて、
倍音とサステイーンに満ちた、厚みの有る音がします。
僕は今までコンパウンド弦を馬鹿にしていましたが
こう言った、ギターには、とても合っています。
サイドバックがハカランダなので、とても固い音ではないかと想像していましたが
音質はマホガニーに近く、とても柔らかで暖かい音がします。
完全に僕好みの音です。
部屋で軽く爪弾くには、最高のギターです。
こう言ったスモールサイズのギターは、大音量で鳴らす事を目的として無く
美しい音を奏でる為のギターだと思います。
このギターをずっと持ち続けるかどうかは
今のところは、まだ分かりませんが
完璧なリペアを施して、最高のコンデションに持って行きたいです。
アコギ好きの友人達に披露するのは、リペアが完了してからにします。
せっかくなので、出品者がアップした写真を紹介します。






Posted by goyaman at 08:00│Comments(18)
│ギター
この記事へのコメント
このギターは、いろいろなメロディーが浮かんできそうですね。
Posted by 村ちゃん at 2013年09月12日 08:07
at 2013年09月12日 08:07
 at 2013年09月12日 08:07
at 2013年09月12日 08:07ご無沙汰しております。
1892年ですか!凄いですね!
1892年ですか!凄いですね!
Posted by ご〜いや〜 at 2013年09月12日 08:34
at 2013年09月12日 08:34
 at 2013年09月12日 08:34
at 2013年09月12日 08:34村ちゃんさん、このギターを弾くと
PPMの歌ばかりを歌ってしまいます。
とても暖かみの有る優しい音色です。
PPMの歌ばかりを歌ってしまいます。
とても暖かみの有る優しい音色です。
Posted by goyaman at 2013年09月12日 10:48
at 2013年09月12日 10:48
 at 2013年09月12日 10:48
at 2013年09月12日 10:48ご〜いや〜 さん、、このギターは100年以上も生き残って来ただけ有って
異次元の深い音です。リペア完了後の音が楽しみです。
異次元の深い音です。リペア完了後の音が楽しみです。
Posted by goyaman at 2013年09月12日 10:50
at 2013年09月12日 10:50
 at 2013年09月12日 10:50
at 2013年09月12日 10:50Goyaman様、19世紀のマーティンゲットおめでとうございます。
私もプリウォーマーティン好きの端くれとして、この頃のマーティンはガット仕様というのをご存知かな?と影ながら心配しておりましたが、流石しっかり勉強されていたようで安心致しました。
大阪WAVERのオーナー本間さんがこの年代のマーティンに相当詳しくていらっしゃいますが、この当時のギターに張る弦はコンパウンドかエクストラライトゲージ(010-の物)がテンション的にガット弦に近いとおっしゃっています。
私はコンパウンドがあまり好きではないのでエクストラライトゲージで代用しております。良かったらご参考になさってください。
私もプリウォーマーティン好きの端くれとして、この頃のマーティンはガット仕様というのをご存知かな?と影ながら心配しておりましたが、流石しっかり勉強されていたようで安心致しました。
大阪WAVERのオーナー本間さんがこの年代のマーティンに相当詳しくていらっしゃいますが、この当時のギターに張る弦はコンパウンドかエクストラライトゲージ(010-の物)がテンション的にガット弦に近いとおっしゃっています。
私はコンパウンドがあまり好きではないのでエクストラライトゲージで代用しております。良かったらご参考になさってください。
Posted by プリウォーマニア at 2013年09月12日 11:35
goyaman様
素晴らしい状態のO-28ですね!
こちらまでドキドキワクワク致します。
リペアに出されるときっとすごい音になるかと思います。
レビュー楽しみにしています。
今日お昼過ぎにOMC-44KLJが届きました。
仕事が終わってから今まで3本のLJと000-28(1965)の弾き比べをして、至福のひとときを過ごしていました。
持ち替えて一番最初に驚いたのはOMC-44KLJのあまりの軽さです。
本当に有り難うございました。
素晴らしい状態のO-28ですね!
こちらまでドキドキワクワク致します。
リペアに出されるときっとすごい音になるかと思います。
レビュー楽しみにしています。
今日お昼過ぎにOMC-44KLJが届きました。
仕事が終わってから今まで3本のLJと000-28(1965)の弾き比べをして、至福のひとときを過ごしていました。
持ち替えて一番最初に驚いたのはOMC-44KLJのあまりの軽さです。
本当に有り難うございました。
Posted by 和歌山のM at 2013年09月12日 18:52
プリウォーマニアさん、コメント有難うございます。
ついに禁断の世界に足を踏み入れてしまいました(笑)
このギターをオークションで見付けた時は
ネットで情報を調べ尽くしました。
僕は1941年製の0-18を持っていますので
それと同じように、太めの弦を張っていたら
大変な事になったと思います。
この頃のギターは、ナイロン弦使用なので
全体的に材が薄く作られていると思います。
それ故に、驚くほど軽く、軽く爪弾いても
倍音とサステイーンに満ちた美しい音がします。
リペアが完了しましたら、エキストラライトゲージも使って見ます。
この頃のギターに対しては、殆ど知識が有りませんので
今後ともアドバイスをよろしくお願いします。
ついに禁断の世界に足を踏み入れてしまいました(笑)
このギターをオークションで見付けた時は
ネットで情報を調べ尽くしました。
僕は1941年製の0-18を持っていますので
それと同じように、太めの弦を張っていたら
大変な事になったと思います。
この頃のギターは、ナイロン弦使用なので
全体的に材が薄く作られていると思います。
それ故に、驚くほど軽く、軽く爪弾いても
倍音とサステイーンに満ちた美しい音がします。
リペアが完了しましたら、エキストラライトゲージも使って見ます。
この頃のギターに対しては、殆ど知識が有りませんので
今後ともアドバイスをよろしくお願いします。
Posted by goyaman at 2013年09月12日 22:16
at 2013年09月12日 22:16
 at 2013年09月12日 22:16
at 2013年09月12日 22:16和歌山のMさん、ついにOMC-44KLJが届いたんですね!!
今回の御茶ノ水回りは、見て回るだけだと思っていましたが
東京に来る前に、試奏して気に入ったギターが有れば
購入予定だったとは、流石です。
OMC-44KLJの素晴らしい音色は、ずっと忘れられません。
ブルーGの店長さんが言われたように、マホとローズウッドの
良いとこ取りのギターだと思います。
僕が手に入れた1923年製の0-18は、これからが大変です。
ネックリセット、ブリッジの圧着、ブリッジプレートも限界にきているようなので
それも取り替え無ければいけません。
一体、幾ら掛かるか分かりませんが、完全にリペアされた
100年前に作られたギターの音を聴いて見たいです。
今回の御茶ノ水回りは、見て回るだけだと思っていましたが
東京に来る前に、試奏して気に入ったギターが有れば
購入予定だったとは、流石です。
OMC-44KLJの素晴らしい音色は、ずっと忘れられません。
ブルーGの店長さんが言われたように、マホとローズウッドの
良いとこ取りのギターだと思います。
僕が手に入れた1923年製の0-18は、これからが大変です。
ネックリセット、ブリッジの圧着、ブリッジプレートも限界にきているようなので
それも取り替え無ければいけません。
一体、幾ら掛かるか分かりませんが、完全にリペアされた
100年前に作られたギターの音を聴いて見たいです。
Posted by goyaman at 2013年09月12日 22:24
at 2013年09月12日 22:24
 at 2013年09月12日 22:24
at 2013年09月12日 22:24goyaman様 マニア歴20年の私からアドバイスすると、戦前モノに手を出されたことによってギター探しの新たなスタートを切られたことをお祝い申し上げます(^^;;
ちなみにナイロン弦の発売は1947年(ナイロンの発明は1930年代)でして、羊の腸を撚って作ったガット弦の代用と一般的には認識されていると思いますが音色やテンションが結構違いまして、多分こちらのギターにナイロン弦を張ってみても大分ボヤけた音になってしまうかと思います。
当時のギター弾きが弾いていた音を再現したいと思って凝ったこともありましたが、本物のガット弦はお金がかかるし寿命も長くないです。でも独特の音の味わいはあります。
ちなみにナイロン弦の発売は1947年(ナイロンの発明は1930年代)でして、羊の腸を撚って作ったガット弦の代用と一般的には認識されていると思いますが音色やテンションが結構違いまして、多分こちらのギターにナイロン弦を張ってみても大分ボヤけた音になってしまうかと思います。
当時のギター弾きが弾いていた音を再現したいと思って凝ったこともありましたが、本物のガット弦はお金がかかるし寿命も長くないです。でも独特の音の味わいはあります。
Posted by プリウォーマニア at 2013年09月12日 23:36
プリウォーマニア様、マニアならではの説明有難うございます。
ナイロン弦以前は、羊の腸で作られた弦で有る事は知っていましたが
ナイロン弦の発売が1947年だとは驚きです。
それほど発売してから年数が経っていないのですね。
僕もガット弦を張って見ようと思っていましたが
現在のクラシックギターのような音色では無いのですね。
所有のギターに、本物のガット弦を張ろうと思ったとの事ですが
本物とは、羊の腸で作られた弦は、今でも売られているのでしょうか?
そうだとしたら、凄いです。
そのような弦で、奏でられた音源を聴いて見たいです。
ナイロン弦以前は、羊の腸で作られた弦で有る事は知っていましたが
ナイロン弦の発売が1947年だとは驚きです。
それほど発売してから年数が経っていないのですね。
僕もガット弦を張って見ようと思っていましたが
現在のクラシックギターのような音色では無いのですね。
所有のギターに、本物のガット弦を張ろうと思ったとの事ですが
本物とは、羊の腸で作られた弦は、今でも売られているのでしょうか?
そうだとしたら、凄いです。
そのような弦で、奏でられた音源を聴いて見たいです。
Posted by goyaman at 2013年09月13日 00:09
at 2013年09月13日 00:09
 at 2013年09月13日 00:09
at 2013年09月13日 00:09ご無沙汰してます。
僕も最近1920年代(らしい)の詳細不明のパーラーギターを買ったばかりなので戦前物のパーラーギターサウンドに興味を持ってます。
というのも、僕のギターはペグもブリッジも付いてない完全ジャンクの代物ですので未だそのサウンドが聴けてません。
ただレッドシダーのTOPにキューバンマホガニーのサイドバックは何が期待させる物があります。塗装も恐らくリフィニッシュされてますがシェラック塗装っぽいのでそちらも期待感を高めます。
気長にリペアして完成したらまたレポしますね。
僕も最近1920年代(らしい)の詳細不明のパーラーギターを買ったばかりなので戦前物のパーラーギターサウンドに興味を持ってます。
というのも、僕のギターはペグもブリッジも付いてない完全ジャンクの代物ですので未だそのサウンドが聴けてません。
ただレッドシダーのTOPにキューバンマホガニーのサイドバックは何が期待させる物があります。塗装も恐らくリフィニッシュされてますがシェラック塗装っぽいのでそちらも期待感を高めます。
気長にリペアして完成したらまたレポしますね。
Posted by 山本 哲平 at 2013年09月13日 01:37
山本 哲平さん、コメント有難うございます。
プリウオーのパーラーギターを手に入れられたのですね。
ペグやブリッジが付いて無いと言う事は格安で購入されたのですね。
ジャンクと言えども、木で作られた楽器ですから
オリジナル製のこだわらなければ、ペグもブリッジも
色んな種類が沢山手に入ります。
素晴らしい材が使われていますから
リペアされて見たらどうでしょうか?
もしかして、ご自分でリペアするつもりでしょうか?
手先が器用で有れば、それも有りですね。
僕の友人はYAMAHAのL-6を20年も掛けて
CUSTOMモデルのようにアバロン貝で、D-45のような
インレイを施しましたが、気長にこつこつリペアするのも
良いかも知れません。
プリウオーのパーラーギターを手に入れられたのですね。
ペグやブリッジが付いて無いと言う事は格安で購入されたのですね。
ジャンクと言えども、木で作られた楽器ですから
オリジナル製のこだわらなければ、ペグもブリッジも
色んな種類が沢山手に入ります。
素晴らしい材が使われていますから
リペアされて見たらどうでしょうか?
もしかして、ご自分でリペアするつもりでしょうか?
手先が器用で有れば、それも有りですね。
僕の友人はYAMAHAのL-6を20年も掛けて
CUSTOMモデルのようにアバロン貝で、D-45のような
インレイを施しましたが、気長にこつこつリペアするのも
良いかも知れません。
Posted by goyaman at 2013年09月13日 01:56
at 2013年09月13日 01:56
 at 2013年09月13日 01:56
at 2013年09月13日 01:56goyaman様 こちらのお店は本物のガット弦を扱っておられます。
http://coastaltrading.biz/
クラシックギター弾きの世界では「19世紀ギター」というのですが、当時の音楽を当時の楽器で弾いて楽しんでおられる方がいらっしゃいます。いいか悪いかは別にして味わい深い独特の音ですよ。弦は高価ですし、スチール弦に比べると高音弦が太くなりますのでナット溝の調整なども必要になるかと思います。
YouTubeではわかりにくいかと思いますが本物のガット弦を張ったギターの音源をリンクしておきます。
http://youtu.be/S5Wop2K5QMM
ちなみにシュタウファーはCFマーティンがドイツ時代にギター作りを学んだ工房ですね。
http://coastaltrading.biz/
クラシックギター弾きの世界では「19世紀ギター」というのですが、当時の音楽を当時の楽器で弾いて楽しんでおられる方がいらっしゃいます。いいか悪いかは別にして味わい深い独特の音ですよ。弦は高価ですし、スチール弦に比べると高音弦が太くなりますのでナット溝の調整なども必要になるかと思います。
YouTubeではわかりにくいかと思いますが本物のガット弦を張ったギターの音源をリンクしておきます。
http://youtu.be/S5Wop2K5QMM
ちなみにシュタウファーはCFマーティンがドイツ時代にギター作りを学んだ工房ですね。
Posted by プリウォーマニア at 2013年09月13日 11:54
連続書き込みですみません。
19世紀ギターを現代の解釈で製作しておられる兵庫県の平山さんのブログも紹介しておきます。
http://kogakki.blog.fc2.com/
ガット弦のことも詳しく書かれています。
ナイロン弦はスチール弦より後に出た弦というのが私も始めビックリしました。
状況に左右されやすいガット弦に不満を持っていた重鎮セゴビアが依頼して、当時の最新素材ナイロンに着目していたオーガスティン社が作ったのがナイロン弦とのことでした。
19世紀ギターを現代の解釈で製作しておられる兵庫県の平山さんのブログも紹介しておきます。
http://kogakki.blog.fc2.com/
ガット弦のことも詳しく書かれています。
ナイロン弦はスチール弦より後に出た弦というのが私も始めビックリしました。
状況に左右されやすいガット弦に不満を持っていた重鎮セゴビアが依頼して、当時の最新素材ナイロンに着目していたオーガスティン社が作ったのがナイロン弦とのことでした。
Posted by プリウォーマニア at 2013年09月13日 12:15
素晴らしい楽器を手に入れられて、おめでとうございます!
goyamanさんのPPMの歌に引かれて、久しぶりに投稿させてもらいます。
私も高校時代にPPMのコピーを必死にやってたので、懐かしいです。
Dont think twiceは、まだ冒頭の歌詞も覚えてます。
goyamanさんの熱意が、希少な縁を引き寄せるんじゃないでしょうか。
凄いです!
goyamanさんのPPMの歌に引かれて、久しぶりに投稿させてもらいます。
私も高校時代にPPMのコピーを必死にやってたので、懐かしいです。
Dont think twiceは、まだ冒頭の歌詞も覚えてます。
goyamanさんの熱意が、希少な縁を引き寄せるんじゃないでしょうか。
凄いです!
Posted by ココパパ at 2013年09月13日 12:21
プリウォーマニア 様、早速教えて頂いたサイトを拝見しました。
弦楽器だけで無く、チエンバロなどの宮廷音楽に使われたような
凄い楽器が紹介されていますね。
早速、YouTubも見ましたが、ナイロン弦とは違って
太く暖かい音がするので、現代でも十分使える弦だと思います。
確かに弦に用いられる、ナイロンと言う材料は
近年になって発明された素材で、今ではストッキングは元より
広く衣服にも使われています。
羊の腸で作られた弦は、ナイロン弦に比べて長持ちはしないでしょうね。
それから、チューニングが安定するまで、時間が掛かりそうです。
湿度や温度にも、変化しそうなので、扱うのは大変そうです。
弦楽器だけで無く、チエンバロなどの宮廷音楽に使われたような
凄い楽器が紹介されていますね。
早速、YouTubも見ましたが、ナイロン弦とは違って
太く暖かい音がするので、現代でも十分使える弦だと思います。
確かに弦に用いられる、ナイロンと言う材料は
近年になって発明された素材で、今ではストッキングは元より
広く衣服にも使われています。
羊の腸で作られた弦は、ナイロン弦に比べて長持ちはしないでしょうね。
それから、チューニングが安定するまで、時間が掛かりそうです。
湿度や温度にも、変化しそうなので、扱うのは大変そうです。
Posted by goyaman at 2013年09月13日 20:25
at 2013年09月13日 20:25
 at 2013年09月13日 20:25
at 2013年09月13日 20:25プリウォーマニア様、現在でも19世紀ギターを復刻して
作っている方が居られるとは、びっくりです。
ギターの前身は、リュートと記憶していますが
現在のクラシックギターの殆どは、スペイン型が殆どなのですね。
ナイロン弦が発明されるまでは、羊や牛の腸が使われていた事
ナイロン弦の出現が、スチール弦より、後で有る事
目から鱗の知識を沢山教えて頂いた事を感謝します。
手に入れた0-28は、100年以上の経年変化で
信じられない位軽いです。
そのように枯れ果てたギターを高温多湿の沖縄の地で
コンデションを保てるか不安です。
以前、ホセ・ラミレス C-650 1963と言うクラシックギターを
沖縄の質屋で手に入れた事が有りますが
このギターも驚くほど軽かったです。
音量が凄まじくて、鉄弦好きの僕なんかが
所有するともったいないと思って、クロサワ楽器で
売って貰いました。
作っている方が居られるとは、びっくりです。
ギターの前身は、リュートと記憶していますが
現在のクラシックギターの殆どは、スペイン型が殆どなのですね。
ナイロン弦が発明されるまでは、羊や牛の腸が使われていた事
ナイロン弦の出現が、スチール弦より、後で有る事
目から鱗の知識を沢山教えて頂いた事を感謝します。
手に入れた0-28は、100年以上の経年変化で
信じられない位軽いです。
そのように枯れ果てたギターを高温多湿の沖縄の地で
コンデションを保てるか不安です。
以前、ホセ・ラミレス C-650 1963と言うクラシックギターを
沖縄の質屋で手に入れた事が有りますが
このギターも驚くほど軽かったです。
音量が凄まじくて、鉄弦好きの僕なんかが
所有するともったいないと思って、クロサワ楽器で
売って貰いました。
Posted by goyaman at 2013年09月13日 22:30
at 2013年09月13日 22:30
 at 2013年09月13日 22:30
at 2013年09月13日 22:30ココパパさん、お久しぶりです。
手に入れた0-28は、弾くと言うより
爪弾くと言った感じのギターです。
鉄弦が存在しなかった頃のギターですので
軽くて、材も薄く作られていますから
腫れ物を扱うように気を使っています。
ボデイの膨らみが有って
弦高がとても高いので、ローフレットを押さえるのも大変です。
リペア後に、どんな音になるのか、不安と期待が入り交じった気持ちです。
しかしながら、このギターを弾いて居ると
PPMの歌ばかり歌ってしまいます。
このギターのコントロールされているかのようです(笑)
手に入れた0-28は、弾くと言うより
爪弾くと言った感じのギターです。
鉄弦が存在しなかった頃のギターですので
軽くて、材も薄く作られていますから
腫れ物を扱うように気を使っています。
ボデイの膨らみが有って
弦高がとても高いので、ローフレットを押さえるのも大変です。
リペア後に、どんな音になるのか、不安と期待が入り交じった気持ちです。
しかしながら、このギターを弾いて居ると
PPMの歌ばかり歌ってしまいます。
このギターのコントロールされているかのようです(笑)
Posted by goyaman at 2013年09月13日 22:39
at 2013年09月13日 22:39
 at 2013年09月13日 22:39
at 2013年09月13日 22:39※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。